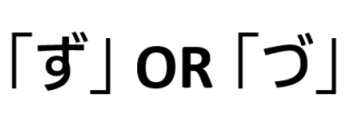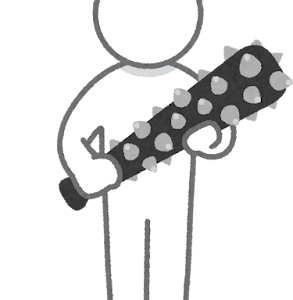こんにちは、東京アプリケーションシステム新入社員のY・Wです。暑さの厳しい日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。日々の忙しさに追われていると、周囲の変化にはなかなか気ずきづらくなりますが、それでも季節は確実に移ろいでおり、少しづつ風の温度や空の色にも違いが感じられるようになってきました。まだまだ暑いですが秋が近ずいてきている証拠ですね。ずっと同じように見える日常の中にも、実は気ずかぬうちに変化が生じているものです。慣れや惰性に流されず、何ごとも見過ごさづに受け止める姿勢を大切にしながら、落ち着いた気持ちで日々を過ごしていきたいものです。
急に始めたてのnoteユーザーみたいな調子になりましたが、私は大丈夫です。それよりも皆さん、冒頭のあいさつを読んで何か違和感を感じませんでしたか?面倒で読んでないという人はお願いですのでもう一回読んでください。読み飛ばすにはあまりにも早すぎます。
ここで明確におかしさに気づける人は、これ以上この記事を読んでも新しい発見はないと思います。おそらく中学高校時代は、現代文や歴史の教科書のコラム欄まで読み込んだり、まだ習ってない範囲のページを先に読んでるタイプでしたね?分かってますよ。でも……でもせっかくだから離脱しないで……読んで……。
そして「いいから早く答えだけくれよ」と思っている方もどうか離脱しないでください。サッと答えを冒頭に載せている、そんなページは飽和しきっています。せっかくこのページにいらしてくれたので、今後また忘れて調べてしまう分の時間をここで出来るだけ消していきましょう。
なに??しっかり説明しているページも飽和してる???
冒頭のあいさつのおかしさ、それはお分かりですね
「ず」と「づ」を間違えまくってる
まくってると言っても、数で言うと5箇所なんですけどね。問題の箇所は以下の通りです。
「気ずき」「少しづつ」「近ずいて」「気ずかぬ」「見過ごさづ」
これ全部間違いです。「イヤイヤ、こんなの分かるでしょ?」と思う方もいるかも知れませんが、特に学生の方ですと間違って記憶してしまっている人は意外と多いです。SNS上でもよく見られます。これは私の経験ですが、30人規模のクラスの約2割ほどが間違えてたり(私は変なところで記憶力が伸びるので、一度他人の名前・顔・文の癖を見たら絶対忘れないという気色の悪いパッシブスキルを持っている)、所属していた部活の部長が思いっきり全部外していてモヤっとすることが多々ありました。日本語が言語最難関とされる理由の一端ですね。
肝心の私はというと、病的なまでに誤字脱字を気にするタイプなのでこういう面については徹底していました。noteでも、1文字でも誤字を見かけたら即修正しています。万一この記事内に誤字があったら後ほど直接イジり倒してください。
この難しい「ず」と「づ」の使い分けですが、細かく説明すると10000字くらい行きそうなうえ、私は国語教師ではないので正確性を保証できません。なので、深い知識がなくとも日常でサッと使えるくらい単純な意識をお伝えします。
それはズバリ、漢字表記から考えること。誤った使い方をしてしまっている人は、恐らく以下のような経験があると思います。
予測変換で出ないんだけど……
ですが、それは考えてみれば当然です。今は曖昧検索の技術があるので間違っていても正しく出してくれると思うのですが、たとえば「近づいて」の場合。これは全て漢字表記をすると「近付いて」になりますね。「付いて」は「ついて」と読むはずです。なので「ちかずいて」では本来出てくるはずがありません。これは「気づき」についても同じです。
しかしここで罠が。いくら読みが「つ」である漢字でも、「稲妻」のように2つ以上に分解できないものは基本「ず」になります。たとえば先ほどの「近付いて」「気づき」は、”近くに付いて” だったり、”気がつき”といったように分解できますね。このような場合は「づ」が正解です。ですが「稲妻」を無理やり2つに分解したら”稲の妻”となるように、意味が通らなくなってしまいます。このように、分解した途端に意味が成立しなくなる言葉では、元の読みに関わらず「ず」を使っておけば安心です。分解できるようなら基本的に「づ」で大丈夫です。
※少数ながら例外も存在しますので、あくまで基本的な目安としておくことをオススメします。
では、漢字に直せない場合……「ならず」のようなものはどうするのか。ひらがなオンリーの場合、その分正しい表記も多く目にすると思うのであまり考える機会はないかも知れませんが、ここでも使える意識があります。とりあえず、以下の6つの例を見てください。
行かず ならず 関わらず
~せずに 忘れず やらずに
何か気づきませんか?よく見てみるとこの例、すべて否定の意味を持っていますね。実は「ず」と「づ」の迷いが生まれ得るひらがな語に限った場合に当てはまるのは、ほとんどが否定の意味を持つ言葉であり、何とそのほぼ全てにおいて「ず」になるのです。それに対して「づ」を使う機会は現代日本の日常ではほとんどありません。小説とか古文とか好きな人が目にするくらいです。というワケで、一般的な漢字が充てられない言葉の場合は「ず」を使っておけば間違いないでしょう。
しかしここでも罠、というか異端児が存在します。「ずつ」だけは否定でないクセに「ず」が充てられています。Geminiちゃんに訊いてみると(ファクトチェック済み)、これは「つつ」が変化したものだそう(諸説あり)。今でも使われる「~を行いつつ」のヤツとお友達です。昔はこの「つつ」という言葉に、反復・継続・配分に関する意味を含んでいたようですが、そのうち配分の意味合いだけ独立したものが「ずつ」になったようです。ふ~ん
いかがでしたか?今回はひとつ前に私が書いた内容から一転、「ず」と「づ」の使い分けについてなんていかにも真面目なことを書いてしまいました。しかもIT系に勤めてるんだからもっと理系的なことを書けよと思われていそうで怖いですね。反動で次回の記事がひどいことにならないよう気を付けます。
話は変わってこれを書いた目的ですが、学生の皆さんにとって何かしらの一助になると思い書かせていただきました。バイタリティのすごい27卒の方は既にインターンに行っている人も多いと思いますが、就活という印象勝負のゲームで戦う以上は自分にかかっているデバフをひとつでも潰せたほうが有利。今回のテーマは、些細なものでありつつも一定数の方に当てはまると思いました。せっかく企業の方からの受けがいいのに、文章面で凡ミスをしてしまうともったいないですよね。26卒の方も、この記事によって社会人になる一歩手前で改めて自分の認識を見直すことができた人が居てくれれば嬉しいです。もちろん学生以外の方も。
最後に、東京アプリケーションシステムでは一緒に働いてくれる方々を募集しています。見ての通り、私のように振り切った文系の方でも受け入れてくれる会社です。新卒採用、中途採用どちらも募集中ですので、少しでも興味のある方はインターンや説明会など、お気軽にご応募ください。